Research
April, 2024 update

研究分野(Research Field)
1、市民性教育の研究
(民主社会における主権者教育論としての学校・教育・学びのあり方の研究)
2、カリキュラム論の研究
(学校教育における教育論、学習論、カリキュラム論の研究)
研究関心 (Research Interests):
何者かがデザインした「理想の社会像」を無批判に伝達・受容する学校・教育ではなく、
自身で社会へ向き合い、批判的・建設的に地域・社会・国家・世界を想像し、創造する。
自ら自律的に社会を描くことができる教育・学校・社会のあり方を研究しています。
研究内容:
・日英米における市民性教育論の比較研究
市民性教育として学校教育を考えています。
「市民性育成論としての教科論の目標・内容・方法の論理とは?」
諸外国のシティズンシップ教育の分析・比較研究を行っています。
・文化を用いた授業のデザイン
「切実性を核とした段階的な市民性育成の論理とは?」
子どもに身近な(そして無意識に巻き込まれている可能性のある)音楽、スポーツ、漫画、映画等、文化現象を用いた教育や学習を考えています。
研究のキーワード:
シティズンシップ教育、市民性教育、カリキュラム研究、教科教育学、社会科教育学、教育方法学
カルチュラル・スタディーズ、対話的教育論、主権者教育論、幼小連携教育論、等

(1)日本社会科教育学会編著『社会科教育事典 第3版』ぎょうせい,2024年
(第3部第3章「哲学・倫理学と社会科」416-417ページを執筆)
●改訂学習指導要領や時代の潮流にマッチした最新の項目を盛り込んだ大改訂。一線の研究者による確かな論考が満載。先行研究の分析、様々な実践の見方や捉え方、教育課程行政、海外の動向など、多くの知見を提供します。
●SDGs、地球環境問題、LGBT、18歳成人、国際紛争問題など、今の社会をどう読み解くかが分かります。1項目見開き2ページ。「現代社会の基礎知識」ともいえる一冊。
●論文制作、基礎研究、授業づくりなど、立場に応じた様々な活用が可能。

(2)土屋武志・白井克尚編著『グローバル社会における解釈型歴史学習』帝国書院,2024年
(第2章第3節「手続きとしての「対話」から原理としての対話へ―解釈型歴史学習の批判的継承―」92-111ページを執筆
第1章 グローバル社会に求められる解釈型歴史学習
第2章 日本における解釈型歴史学習の展開
第3章 アジアにおける解釈型歴史学習の展開
第4章 欧米における解釈型歴史学習の展開
第5章 グローバル社会における解釈型歴史学習の実践

(3)小玉重夫監修・田中伸・豊田光世編著『対話的教育論の探究-子どもの哲学が描く民主的な社会-』東京大学出版会、2023年
(「はじめに」pp.1-10ページ,第7章「学びの『機能』から『作用』へ-学びの構造を転換するための探究カリキュラム-」pp.39-170、を執筆)
「Philosophy for Children(P4C/子どもの哲学)」が掲げる「民主的な社会の実現」は教育とのいかなる調和の下で可能になるのか。特に教育の現場で得られた知見に基づきながら、P4Cが重視する「対話」が教育実践においていかにあるべきかを探る。
https://www.utp.or.jp/book/b10033303.html(東京大学出版会Website):「はじめに」の試し読みが可能です。

(4)二井正浩編『レリバンスを構築する歴史授業の論理と実践』風間書房、2023年
(第7章「目的動機(行為)と理由動機(反省)から見た学びの可能性と有意味性-子どもは歴史授業に何を見たのか-」181-211ページを執筆)
古くて新しい歴史教育におけるレリバンス問題をテーマに、国内外の授業実践、授業づくり、カリキュラム改革等を分析し、歴史教育の変革を展望する。

(5)伊藤直之編『地理歴史授業の国際協働開発と教師への普及』風間書房、2022年
(第4章「汎用的な資質・能力」77-86ページを執筆)
高校新科目「地理総合・歴史総合」を見据え資質・能力の多様性と学際性を視点に地理歴史教育論を体系化。新たな授業実践を創造する。

(6) 田中伸・山田秀樹監修,公益財団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会編著『18歳からのスマート通販学』アマゾンジャパン合同会社,2022年
「18歳からのスマート通販学」は、インターネット通販において、トラブルにつまずくことなく優雅にかわし、買い物をのびのび楽しむ大人のスタイルの実現に向けて身につけたい知識や心構えを学び、スマートな大人の振る舞いを目指すための新教材です。
https://www.amazon.co.jp/dp/B09R7HKNYK/
(2023年5月現在、無料ダウンロード可能です)

(7)棚橋健治、木村博一編『社会科重要用語事典』明治図書、2022年
(「批判主義」46-47ページ,「クリック・レポート」57ページ,「コミュニケーション」73ページ,「共和主義とコミュニタリアニズム」79ページ,「カリキュラム・マネジメント」124ページ,「レリバンス」126ページ,「イギリスの社会系教科教育」224-225ページを執筆)
社会科教育・実践の動向を視野に入れ、これからの社会科教育を考える際に重要な術語を厳選。特質や目標・授業づくり・指導法・歴史等、その基礎知識をコンパクトに解説。不変的な用語のみならず、新しい潮流も汲んだ、社会科教育に関わるすべての人にとって必携の書。

(8)2022年、二井正浩編著『レリバンスの視点からの歴史教育改革論』風間書房
(第3章「レリバンス論とその射程」53-74ページを執筆)
学ぶ意味や意義を子どもが実感できる歴史学習とはどのようなものか。本書は日・米・英・独の事例を手がかりにレリバンスの視点から歴史教育の改革を提言する。

(9)国分麻里、川口広美編『新・教職課程演習 第17巻 中等社会系教育』協同出版、2021年
(第2章Q2「カリキュラムマネジメントについて説明しなさい」33-36ページを執筆)
目次
第1章 中等社会系教科の目標
第2章 中等社会系教科のカリキュラム
第3章 中等社会系教科における「見方・考え方」と学習指導法
第4章 中等社会系教科の学習評価法
第5章 地理の教材研究の視点
第6章 歴史の教材研究の視点
第7章 公民の教材研究の視点
第8章 中等社会系教科の教師の職能成長
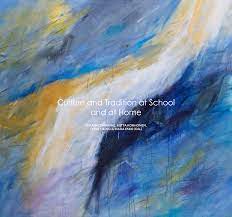
(Part1 Culture and Tradition for Education内“ A New Approach to Teaching and Learning Culture in Modern Society: A Case of Educational Practice in Japan”, 38-49ページを執筆)
https://tuhat.helsinki.fi/ws/files/172606550/Culture_and_Tradition_at_School_and_at_Home.pdf
(2023年5月現在、open access)
Contents Culture and Tradition at School and at home
Introduction 6
Mika Metsärinne & Riitta Korhonen
I Part: Culture and Tradition for Education
Local Heritage as an Identity Builder 14
Heljä Järnefelt
Craft science and –education cultural dimensions* 28
Mika Metsärinne
A New Approach to Teaching and Learning Culture in Modern Society: A Case of Educational Practice in Japan 38
Noboru Tanaka
Culture at school and at home 48
Risto Kupari
Enhancing home and school links through culture and tradition connections 54
Julia Athena Spinthourakis
‘Using History with young people'? 72
Søren Hegstrup
Culture Keeping in Urban Dispersed Ethnic Communities 80
Sharon Rae Landergott Durtka & Alexander P. Durtka
II Part: Case studies about Cultural Education
What objects do 6th grade pupils decide to draw in an old museum?* 104
Ari Vanhala & Mika Metsärinne
The Rauma teaching garden as a cultural heritage milieu and place to grow 114
Inkeri Ruokonen & Jaana Lepistö
Outdoor School and Forest School Preliminary analysis in three municipal Nursery Schools in Rome 128
Sandra Chistolini
Cultural heritage and social learning: the case of Heritage Hubs project* 140
Aleksandra Nikolic, Kati Nurmi & Mariola Andonegui Navarro
III Part: Perspectives on Culture Heritage
The Role of Traditions in Living Together in a multicultural society. A conceptual and operational vision 158
Cyrill Renz
Yours, mine or ours? – Who does cultural heritage belong to? 176
Ira Vihreälehto
Ornament as a Personality Growth and Non-verbal Content Guideline Research Tool. 182
Māra Vidnere & Sandra Rone
The Adinkra game: an intercultural communicative and philosophical praxis 192
Louise Müller, Kofi Dorvlo & Heidi Muijen
Folk-dancing Communities - Participation through Tradition, Creativity, and Dance Technique* 224
Petri Hoppu
The traditions of dolls and mascots to promote cultures. 234
Hugo Verkest & Ebru Aktan Acar
IV Part: Teacher Training School in Rauma
Department of Teacher Education and Teacher Training School, Rauma at the University of Turku 254
Tapio Heino
Versatile educational opportunities in a garden environment for teacher trainees 258
Teija Koskela, Outi Kokkonen, Kirsi Urmson, Mia Koivuniemi, Ville Turunen, Karoliina Saurio, Marketta Kortelahti & Heli Keinänen

(11)M.Rグレゴリー他著、小玉重夫監修 豊田光世、田中伸、田端健人訳者代表『子どものための哲学教育ハンドブック-世界で広がる探究学習-』東京大学出版会、2020年
1. (「第3章 市民の教育:熟議の教育論を追究するハワイのp4c」55-70ページ,「Part4 実践する探求のコミュニティー-認識論とペタゴジー-」139-140ページ,「訳者解説『子ども,学校,そして社会の可能性を拓く』」343-356ページを執筆)
http://www.utp.or.jp/book/b517255.html(東京大学出版会)
子どもたちの主体的な探究を育む教育実践の最先端を,理念と手法の両面から展望する.日本でもよりいっそう「対話」「思考」「探究」などの価値が重視されるなか,人として生きるうえで重要な「考える力」の育成という,世界的な教育の目標実現のための手引きとなる書.

(12)日本教科教育学会編『教科とその本質-各教科は何を目指し、どのように構成するのか-』教育出版、2020年
(第4章第3節「市民科とはどのような教科か」170-175ページを執筆)
目次
第1章 教科とは何かー佐藤学、池野範男による対談/第2章 教科の役割と意義を考える(教科とは何か、どのようなものか:教科の定義/学校において、教科がなぜ必要とされるのか:教科の存立根拠/なぜ各教科等における領域や区分はあるのか ほか)/第3章 各教科とその本質を考える(国語科とはどのような教科か/社会科とはどのような教科か/算数・数学科とはどのような教科か ほか)/第4章 学校設定教科の本質を考える(「記号科」とはどのような教科か/「てつがく」とはどのような教科か/市民科とはどのような教科か ほか)

(13)社会認識教育学会編『中学校社会科教育・高等学校公民科教育』学術図書出版社、2020年
1. (第5章「中学校社会科・高等学校公民科教育のカリキュラムデザイン-教科の目標と達成するためには何をどのような順で学ぶのが良いのかを,どのように考えるか」49-60ページを執筆)
本書は,中等教育段階における社会認識教育についての研究・実践の入門書として編集されたもので,本書で扱うのは,学校教育における現行の教科でいえば,中学校社会科と高等学校公民科である.
本書では,「社会認識を通して市民的資質を育成する」教科とされるこれまでの社会認識教育学研究の成果に基づき,今,この社会で求められるべき中学校社会科教育,高等学校公民科教育について多面的・多角的に考察した.

(14)子どものシティズンシップ教育研究会『社会形成科社会科論ー批判主義社会科の継承と革新』風間書房、2019年
(第1章2「批判主義社会科の目標論」14-28ページを執筆)
批判主義社会科論の更なる再構築に向けて
本書は批判主義社会科論研究の第一人者である池野範男氏の研究を、ただ単に「後追い」するのではなく、その研究を対象化し、それを批判的に検討することが批判主義の社会科論、ひいては、日本の社会科教育研究を革新することになると信じ、各執筆者が渾身を込めて論じたものである。本書の出版が、社会科教育研究者のみならず、社会科教員、それを目指す院生・学生の研究推進の一助になれば幸いである。(本書「まえがき」より)

(15)原田智仁編著『平成30年度版 学習指導要領改訂のポイント 高等学校地理歴史公民』明治図書、2019年
(第1章「カリキュラム・マネジメント」58-61ページを執筆)
大改訂の学習指導要領を徹底解説!
学習指導要領の大改訂で新科目編成となった高等学校地理歴史科、公民科をキーワードと事例で徹底解説。見方・考え方から新設科目のポイント、地理・歴史・公民の方向性と課題、カリキュラム・マネジメントから、主体的・対話的で深い学びを促す授業展開例までを網羅。
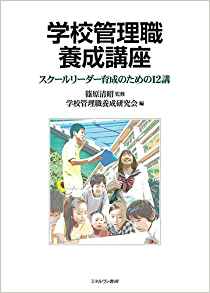
(16)篠原清昭編『学校管理職養成講座』ミネルヴァ書房、2018年
1. (第11講「授業開発論」169-182ページを執筆)
12領域を3ユニットで体系的・実践的に学ぶ、最新の管理職養成・研修テキスト
2018年度から教員のみならず学校管理職(校長、教頭)の育成指標の作成とそれに基づく学校管理職研修の事業化が始動した。本書は、この指針を的確に踏まえた上で、個別的な学問領域に限定された専門的記述ではなく、今後全国で必要とされる学校管理職研修講習のテキストとして、さらに学校管理職及び中堅教員を養成する全国の大学院のテキストとしても汎用性ある内容構成となっている。

(17)須本良夫編著『調停する力を引き出す道徳教育の展開』デザインエッグ社、2018年
(第4章「社会科教育研究者が語る調停−“調停教育”に陥らないために-」46-55ページを執筆)
いじめ,隣のペットの鳴き声がうるさい,交通事故の過失割合,ママ友だと思っていたのにLINEで相手にされない,家の横に急迷惑な施設が建される,兄弟で親の介護を押し付け合うをはじめとする社会の問題の数々。解決はそうたやすくなく,時には裁判沙汰に。学校のいじめも少なくならない昨今,少しでも問題を減らすトレーニングの教育があってもいいのでは。それが,調停する力を育成する教育。本書では,その理論から実践,様々な立場の研究者や弁護士が調停を明らかにしています。

(18)須本良夫・田中伸編『社会科教育におけるカリキュラム・マネジメント~ゴールを基盤とした実践及び教員養成のインストラクション~』梓出版社、2017年
(「はじめに−教師を『理想主義』から解き放つ思想−」ⅰ-ⅳ,第1部「社会科教育におけるカリキュラム・マネジメント」2-21ページを執筆)
本書の特徴は、以下二点です。第1は、内容(contents)ではなく、能力(goal)ベースの授業デザインの方略を示しています。それも、理想的な指導案を並べるものではなく、実際に実践した指導案をネタに、子どもの切実性・学校組織・同僚性や社会諸科学の学問成果などをどのように仕掛けることで、どのような授業が展開できるのか。教師や子どもが置かれている社会的・文化的文脈に着目した授業の作り方を検討しています。
第2は、教員養成のあり方を論争的に示しています。今回は授業力に着目し、大学・学校現場・教育委員会・学会組織などは、どのような授業力をどのように育成しているのか。様々な主体へ「育成が求められる授業力」を自由に語ってもらいました。そのため、各主体の主張が極めて論争的になっています。

(19)原田智仁・關浩和・二井正浩編『教科教育学研究の可能性を求めて』風間書房、2017年
1. (第Ⅱ章第4節「社会科教育による社会的レリバンスの構築―コミュニケーション理論を用いた授業開発方略―」105-114ページを執筆)
教科教育学研究における課題として、授業研究、教師教育、カリキュラム・マネジメント、資質・能力(コンピテンシー)、アクティブ・ラーニングなどの鍵概念を示して、今後の研究のあり方を提案する。

(20)原田智仁編『社会科教育のルネサンスー実践知を求めてー』保育出版社、2016年
(第4章1節「社会科の授業デザイン」68-71ページを執筆)
ケンシロウなら,即座に宣告するに違いありません。「お前はもう死んでいる!」と。そうした状況に目をつぶって,社会科教育の表面的な延命を図ったとしても未来はないでしょう。誰かに宣告される前に,まず自ら瀕死の状態にあることを自覚し,再生・復活を目指して不断の授業改善に取り組むしか方法
はないのです。そうした改善の営みのなかから,やがて社会科教育のレオナルド=ダ=ヴィンチやミケランジェロが出てくると期待し,そう願って,再生・復活のための処方箋を具体事例とともに分かりやすく解説しました。(「編者のことば」より抜粋)
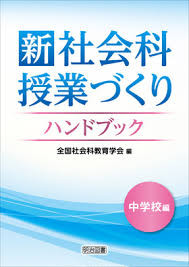
(21)2015年、全国社会科教育学会編『新 社会科授業づくりハンドブック』明治図書、2015年
(フレッシュ教員のQuestion &研究者のAnswerページ③「見方・考え方の育成はどこまで必要か?」84ページを執筆)
開発された具体的な社会科授業を紹介し、その授業開発のプロセスや留意点、さらには研究者・メンターによる講評も収録した画期的な一冊。教員を志す学部生・大学院生から、現職教員、教員養成に携わる大学教員まで、中学校の社会科教育関係者、必読の書。(明治図書 紹介文)

(22)草原和博・溝口和宏・桑原敏典『社会科教育学研究法ハンドブック』明治図書、2015年
(第Ⅱ部3章「海外研究誌に学ぶ斬新な研究」145-161ページを執筆)
社会科教育(社会認識教育)学の論文の作り方・書き方を、近年の研究動向を踏まえて大きく3つの類型に整理し、具体例を交えながら解説。研究計画の立て方から論文の組み立て方まで、研究デザインの仕方が基礎からすべてわかる。
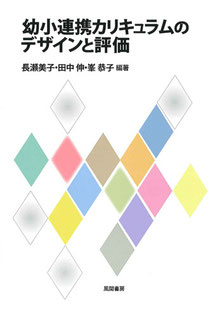
(23)長瀬美子、田中伸、峯恭子『幼小連携カリキュラムのデザインと評価』風間書房、2015年
(「はじめに」ⅰ-ⅴ,第2章「幼小連携に基づくカリキュラム・デザインの理論と方法」15-32ページを執筆)
幼稚園教育と小学校教育の独自性を保ちつつ教育目標に連続性を持たせた連携カリキュラムを構想。小学校の教科別に幼小連携の視点を示し、指導計画と評価の観点を提案する。
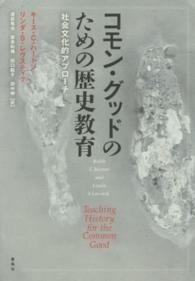
(24)キース・C・バートン、リンダ・S・レヴスティック著、渡部竜也、草原和博、田口紘子、田中伸訳『コモン・グッドのための歴史教育ー社会文化的アプローチー』春風社、2015年
(第7章「物語の構造と歴史教育」201-230ページを共同で執筆,第9章「国家の自由と進歩の物語」253-282ページを単独で執筆)
子どもたちの歴史的思考はいかに促されるべきなのか。そのための教師のあるべき姿は?
アメリカ合衆国、北アイルランド、ニュージーランドを事例に、
多元主義的民主主義への参加に貢献するための歴史教育を根源から問い直す。

(25)棚橋健治編『教師教育講座 中等社会系教育』協同出版、2014年
(第4章「中等社会系教科の本質—社会的思想の習得を中核に位置付ける教科論—」63-82ページを執筆)

(26)長瀬美子、田中伸、峯恭子編『幼児教育におけるカリキュラム・デザインの理論と方法』風間書房、2014年
(「はじめに」ⅰ-ⅲ,第4章「領域『人間関係』を軸としたカリキュラム・デザイン」51-78ページを執筆)
2016年重版(第2版刊行 )
5領域の視点から、幼児教育における年間カリキュラムの設計方法や評価の観点について具体的に提案する。ノンカリキュラム論からの転換を目指した実践的な手引き書。

(27)長瀬美子、小谷卓也、田中伸編『幼児教育学実践ハンドブック』風間書房、2013年
(「はじめに」ⅰ-ⅲ,第3章第3節「幼児教育カリキュラムの類型と実際」43-52ページ, 第6章第2節「教員養成カリキュラムスタンダードの開発と展望」138-145ページを執筆)
2015年重版(第2版刊行 )
保育者を志す学生、現職教員を対象に、常識として踏まえておきたい事や近年の研究動向、実践の蓄積等をコンパクトにまとめた、一冊で分かる幼児教育学ハンドブック。

(28)Stephen J. Thornton著、渡部竜也、山田秀和、田中伸、堀田諭共訳『教師のゲートキーピング−主体的な学習者を生む社会科カリキュラムに向けて−』春風社、2012年
(第5章「教育方法」101-118ページ,第7章「実際なされているカリキュラムの重要性」139-144ページを執筆)
2016年重版(第2版刊行 )
カリキュラム改革を実施しても、教師のゲートキーピング力(=カリキュラム調節能力)を磨かなければ教室は変わらない。米国社会科教育史における論争を展望し、教育の根本を押さえつつ、カリキュラムを柔軟に運用する教師像を模索する。

(29)兵庫教育大学教員養成スタンダード研究開発チーム著・別惣淳二、渡邊隆信編『教員養成スタンダードに基づく教員の質保証—学生の自己成長を促す全学的学習支援体制の構築—』ジアース教育新社、2012年
(補論第2節「海外の教員養成スタンダードの現状 イギリス」214-218ページを執筆)
教員養成教育によって学生が何を理解し、何ができるようになったかを重視する視点から教員養成スタンダードを開発、学生の自己成長を促す全学的学習支援体制を構築するためのモデルを提示。スタンダード導入後の学生の意識の変化も検証し、教員養成段階における教員の質保証を考える。

(30)全国社会科教育学会編『社会科教育実践ハンドブック』明治図書、2012年
1. (第8章第2節「社会空間形成としての地理学習」149-152ページを執筆)
社会科教育実践に関する基礎概念を明確化。「問題解決」「理解」「説明」議論」「意思決定」「社会参加」といった授業原理の視点から、新しい社会科教育実践の実例を多く紹介するとともに、問題解決の方策を提案。教師自身が自己の社会科教育実践力の向上を図っていくための方法も示唆。
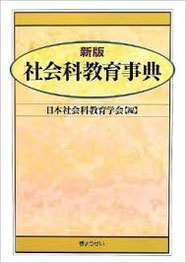
(31)日本社会科教育学会『新版社会科教育事典』ぎょうせい、2012年
(第3部第2章「アメリカの社会科の動向」356-357ページを執筆)
社会科教育に関する用語225項目を取り上げ、1項目見開き2ページで解説。「社会科の基礎論」「社会科の実践論」「現代社会からの発信」の3部構成。社会科教育史年表を付録として収録。

(32)田中伸『現代アメリカ社会科の展開と構造—社会認識教育論から文化認識教育論へ』風間書房、2011年
1960年代以降のアメリカ社会科教育の論理的構造転換を、学問・教育・社会の変化という背景的要因、並びに具体的な学習の変化という実体的分析に基づいて解明した著書。

(33)社会認識教育学会編『新社会科教育学ハンドブック』明治図書、2011年
(第8章(2)「小学校における社会科授業(2)」392-401ページを執筆)
誰も反対しない“民主主義の実現”に向かって邁進してきて、フト立ち止まっている現代。いったい社会とは何かグローバルに考えなければならない今日、複雑な要因のからみ合いの中から紐解くモノサシを、学会に集う研究者が総出で解明した話題作。

(34)社会認識教育学会編『改訂新版 地理歴史科教育』学術図書、2010年
(第7章第3節「世界史教育における課題と論争点」153-161ページを執筆)

(35)日本公民教育学会編『公民教育事典』第一学習社、2009年
(第5章「『情報社会』の学習」148-149ページを執筆)
公民教育の原理を幅広く扱うとともに,政治,経済,倫理,社会等の公民教育の諸領域について項目を設定。公民教育で実施される学習活動や学習の評価,公民教育と関連する諸科学についても項目を設定。
(1)岩橋嘉大,中山智貴,行寿浩司,福田喜彦,田中伸,吉水裕也「社会的レリバンスを構築する社会科公民の授業開発-子どもの未来イメージに着目して-」『教育学部研究紀要(人文科学)』岐阜大学教育学部,第72巻第2号,2024年,pp.21-30
(2)中山智貴,行寿浩司,田中伸,吉水裕也「レリバンスの構造転換に着目した社会科地理授業(2)」『教育学部研究紀要(人文科学)』岐阜大学教育学部,第72巻第1号,2023年,pp.55-64
(3)田中伸「『民主主義の実践』が拓く,希望」『Voters』公益財団法人明るい選挙推進協会,76号,2023年,pp.12-15
(4)田中伸「『社会』と括ることの危うさ,暴力性を考える」『社会科教育』明治図書,2023年,pp.38-39
(5)田中伸「ポスト・トゥルース時代,教育に何ができるか」『教室の窓』東京書籍,vol.26,2023年,pp.5-6
(6)福井駿、藤井佳世、田中伸、田端健人「対話的な学びとコミュニティ形成-討議倫理とP4Cの視点からの事例検討-」『岐阜大学研究紀要』第71巻1号、2022年、pp.75-85
(7)中山智貴、行寿浩司、田中伸、吉水裕也「レリバンスの構造転換に着目した社会科地理授業(1)」『岐阜大学研究紀要』、第70巻第2号、2022年、pp.21-30
(8)Noboru TANAKA, Ritta Korhonen, Tapio Heino, Mika Metsarinne, Professors' views regarding their professional careers, identities, and educational work: Comparative research between Japan and Finland, Journal of Social Studies Lesson Study, 8(2), 2021. pp.127-139
(9)辻本諭、田中伸、三浦寛之「教師・歴史学者・社会科教育学者が協働した授業のゲートキーピング(2) -P4Cを用いた歴史教育実践:移民を考える–」『岐阜大学教育学部研究報告』Vol.45、2021年、pp.23-32
(10)Noboru TANAKA , Social Studies Education Utilizing Children's Motivations: Methodology to Connect Children and Society Through the Dismantling of "Performed Consensus" ,The Journal of Social Studies Education in Asia, Vol.9, 2020, pp.13-26
(11)田中伸「学際性にもとづく資質・能力論-汎用的な資質能力:現象的学習論(Phenomenal Learning)-」伊藤直之「資質・能力の多様性と学際性を視点にした地理歴史授業の国際協働開発と教師への普及」科学研究費補助金研究成果報告書(17H02704)、2020年
(12)Amber Strong Makaiau, Noboru Tanaka"Philosophy for Children: A Deliberative Pedagogy for Teaching Social Studies in Japan and the USA". Journal of International Social Studies, National Council for the Social Studies International Assembly, v.8, n.2, 2018, pp.29-54
(13)田中伸・Amber Strong Makaiau「探究学習における対話の原理-グローバル時代における社会科教育研究方法論の提案を通して-」『社会科教育研究』日本社会科教育学会、2018年、pp.72-85
(14)田中伸・辻本諭・前田佳洋・矢島徳宗「教師・歴史学者・社会科教育学者が協働した授業のゲートキーピング- 歴史学の思考・方法を活用した解釈を主体とする歴史教育実践–」岐阜大学教育学部研究紀要、67巻第1号、2018年、pp.41-53
(15)田中伸「子どもが無意識に持つ『コモン・グッド』を暴き、分析する社会科」『社会科教育』明治図書、2018年9月号、pp.124-125
(16)田中伸「『考える社会科』はじめの一歩-批判的思考を養う第一手- 『批判』を教えるか、批判的に思考するか?」『社会科教育』明治図書、2018年5月号、pp.26-29
(17)岡田了祐・堀田諭・村井大介・渡邉巧・田口紘子・田中伸「米国の教師教育者にみるprofessional identityの多様性-社会科教育を事例とした教科観と教師教育者観に着目して-」『教育実践研究・教師教育研究』岐阜大学教育学部、第20巻、2018年、pp.57-67
(18)田中伸、橋本康弘「高等学校社会系教科目における価値学習の実態と課題-生徒の価値判断基準とその変容の分析を通して-」『法と教育』法と教育学会、2017年、pp.5-15。
(19)田中伸「社会的レリバンスの構築を目指した授業研究の方略ー米国社会科教育は子どもの学びへの動機をどのように扱ってきたかー」『社会科教育論叢』全国社会科教育学会、2017年、pp.81-90
(20)田中伸・前田佳洋・矢島徳宗「社会科教育実践における教師のゲートキーピングー消費者市民社会の構築を目指した学校と社会のコミュニケーションー」『岐阜大学教育学部研究紀要』第65巻2号、2017年、pp.37-49
(21)田中伸、高木友美、北川住江「消費者市民社会の構築を目指した教育実践開発方略ー未来社会の創造を目指した主権者育成論としての消費者教育実践ー」『岐阜大学教育学部研究紀要』第65巻1号、2016年、pp.39-52。
(22)田中伸「小学校6年『他教科とクロスする』アクティブな授業モデル-スポーツの分析を通した社会の探究:子どもの常識を疑う文化学習-」『社会科教育』明治図書、2016年8月号、pp.72-75。
(23)田中伸「主権者教育は何から始めればよいのかー授業デザインのヒントー『形式主義に陥ってはいけない。現実社会の文脈で熟議する学習を!』」『社会科教育』2016年6月号、pp.12-13。
(24)森川敦子・須本良夫・田中伸「問題解決能力を育成する道徳教育に関する基礎的研究—ハワイ州のピア・メディエーション授業をもとに—」『比治山大学・比治山大学短期大学部教職課程研究』、第2巻、2016年、pp.98-108。
(25)Noboru TANAKA, History Learning as Citizenship Education; Collaborative Learning based on Luhmann's Theory of Communication, The Journal of Social Studies Education, The International Social Studies Association, Vo.5, 2016, pp.57-70.
(27)田中伸「コミュニケーション理論に基づく社会科教育論ー『社会と折り合いをつける力』の育成を目指した授業デザインー」『社会科研究』全国社会科教育学会、2015年、pp.1-12
(28)Noboru TANAKA, “Differences between Citizenship Awareness in Japan and UK -How students argue on controversial issues -”, in P. Cunningham & N. Fretwell (eds.) Innovative Practice and Research Trends in Identity, Citizenship and Education, London: Children’s Identity and Citizenship European Association, 2014年, pp.43-55
(29)田中伸「カルチュラル・スタディーズに基づく社会科授業のデザイン—エンコーディング・デコーディング理論を用いたメディア単元の開発を通して—」『教育学部研究紀要(人文科学)』岐阜大学教育学部、63巻、1号、2014年、pp.23-36
(30)田中伸「文化研究に基づく地歴総合の論理―意味理解型文化研究学習論におけるカリキュラム・授業構成―」『中等社会系教科における歴史総合・地歴相関カリキュラムに関する国際調査・開発研究』科学研究費補助金基盤研究B研究成果報告書,2014年、pp.19-32。
(31) Noboru TANAKA, “Teaching about Plurality of perspectives: Educational practices in Japanese schools teaching social sciences, The Journal of Social Studies Education, The International Social Studies Association,Vol.3, 2014, pp.91-103
(32)草原和博、渡部竜也、田口紘子、田中伸、小川正人「日本の社会科教育研究者の研究観と方法論-なんのために,どのように研究するか-」『教科教育学研究』日本教科教育学会、第37巻第1号、2014年、pp.63-74(共著)
(33)田中伸、草原和博、渡部竜也、田口紘子、小川正人「日本の社会科教育研究者の研究観と方法論(2)-教科教育学研究者が目指すべき研究スタイルと理想像-」『大阪大谷大学紀要』大阪大谷大学第48号、2013年、56-75。
(34)Takuya Kotani, Noboru TANAKA Yoshiko Nagase, and Kyoko Mine, "Kindergarten Science in the United States and Japan", Foss Curriculum Developer, FOSS Newsletter, No.40, 2012, pp.5-7.
(35)Noboru TANAKA, “The methodological differences between Japanese and British research on citizenship education”, in P. Cunningham & N. Fretwell (eds.) Creating Communities: Local, National and Global, London: Children’s Identity and Citizenship European Association, 2012年12月, pp.81-93
(36)田中伸「英国市民性教育研究の方法論的特質−3つのアプローチにみられる研究目的・内容・方法の特質と課題−」『社会科教育論叢』全国社会科教育学会、第48集、2012年、pp.87-96
(37) Noboru TANAKA, “The Structure of Learning Environments in Elementary Social Studies Education Aimed at Methodology of Inquiry: Educational Practice for Citizenship through Analysis of Media Used”, The Journal of Social Studies Education, The International Social Studies Associationl, 2012, Vol.1,pp.1-10.
(38)田中伸「シティズンシップ教育実践の多様性とその原理−学習環境を規定する市民性意識の解明を通して−」『教育方法学研究』日本教育方法学会、第36巻、2011年、pp.39-50。
(39)Noboru TANAKA, “The relations of citizenship and the educational practice in Japan-in the educational practice of “law related education”-”, in P. Cunningham & N. Fretwell (eds.) Lifelong Learning and Active Citizenship, London: Children’s Identity and Citizenship European Association, 2010, pp.276-287
(40)田中伸「言葉は深化する」『社会科教育』明治図書,2010年8月号,10ページ
(41)田中伸「教育研究において学際的協同はいかにして可能となるかーデザイン科学としての社会科教育」『教育学研究紀要』中国四国教育学会、第55巻、2010年、pp.702-707
(42) Noboru TANAKA, “Research about the nature of citizenship in Japan”, in Ross, A. (eds.) Human Rights and Citizenship Education,London: Children’s Identity and Citizenship European Association, 2009年, pp.244-250
(43)田中伸「社会科教育学研究における研究方法論の検討―PISA調査結果を基盤とした学際的恊働への布石」『教育学研究紀要』中国四国教育学会、第54巻、2009年、pp.728-733。
(44)田中伸「地理で使える超有名レプリカ教材10」『社会科教育』明治図書,2009年9月号,14-15ページ
(45)田中伸「関心相関性に基づく授業構成論—英国シティズンシップ教育とわが国の社会科教育の相違—」『日本社会科教育学会全国大会発表論文集』日本社会科教育学会、第4号、2008年、pp.100-101
(46)田中伸「小学校社会科文化学習の改善-知識を受容する学習から意味を解釈する学習へー」『兵庫教育大学研究紀要』兵庫教育大学、第33巻、2008年、pp.173-183
(47) 田中伸「構造主義に基づく批判の論理-1970年代におけるアメリカ社会科文化学習を事例としてー」『社会認識教育学研究』鳴門社会科教育学会、第23号、2008年、pp.1-10
(48) 岩田一彦、田中伸「世界に関わる空間軸の形成-学習指導要領の歴史的分析を通してー」『兵庫教育大学教科教育学会紀要』兵庫教育大学教科教育学会、第21巻、2008年、pp.3-12
(49) Noboru TANAKA“Citizenship education in Japan”, Teaching Citizenship, Association for Citizenship Teaching, issue19, 2007, pp.46-49
(50)Noboru TANAKA“Concept of Aesthetic Education”, British Journal of Educational Studies, Vol.55, No.4, December, 2007, pp.19-20
(51) 池野範男、竹中伸夫、柳生大輔、田口紘子、田中伸、二階堂年恵、丹生英治「認識変容に関する社会科評価研究(4)-中学校歴史単元『喧嘩両成敗について考える』学習の評価分析-」『学校教育実践学研究』第13号、広島大学大学院教育学研究科附属教育実践総合センター、2007年、pp.63-73
(52)田中伸「現代アメリカ社会科の論理と展開-社会認識教育論から文化認識教育論へ」広島大学大学院教育学研究科(博士論文)、2007年
(53) 丹生英治、田中伸、二階堂年恵、田口紘子「見方・考え方を育てる中学校地理授業の開発-小単元『家族と空間について考える』の場合-」『広島大学大学院教育学研究科紀要』第2部、広島大学大学院教育学研究科、第55号、2007年、pp.107-115
(54) 田口紘子、竹中伸夫、田中伸、丹生英治「見方・考え方を育てる中学校歴史授業の開発-『喧嘩両成敗について考える』の場合-」『広島大学大学院教育学研究科紀要』第2部、広島大学大学院教育学研究科、第55号、2007年、pp.117-126
(55)田中伸「構築主義に基づく社会科授業の特質-文化研究の視点から-」『平成18年度地理歴史・公民部会研究紀要』広島県高等学校教育研究会地理歴史・公民部会、2007年、pp.57-70
(56)池野範男、竹中伸夫、田中伸、二階堂年恵、丹生英治、田口紘子「認識変容に関する社会科評価研究(3)-中学校公民単元『国際連合について考える』学習の評価分析-」『学校教育実践学研究』広島大学大学院教育学研究科附属教育実践総合センター、第12巻、2007年、pp.267-282
(57)田中伸「批判の論理に基づく構造主義的文化学習の特質-教科書『人類学の探究』を事例として-」『日本社会科教育学会全国大会発表論文集』日本社会科教育学会、第2号、2006年、pp.122-123
(58)田中伸「解釈構築の論理に基づく文化研究学習-教科書『文化の創造(Create a Culture)』を事例として-」『社会系教科教育学研究』社会系教科教育学会、第18号、2006年、pp.47-54
(59)池野範男、竹中伸夫、田中伸、二階堂年恵「認識変容に関する社会科評価研究(2)-小学校地図学習の評価分析-」『学校教育実践学研究』広島大学大学院教育学研究科附属教育実践総合センター、第1巻、2006年、pp.255-265
(60)田中伸「構築主義に基づく文化研究学習原理-アメリカ文化学習教科書『世界への窓』を事例として-」『社会科研究』全国社会科教育学会、第64号、2006年、pp.81-90
(61)池野範男、竹中伸夫、田中伸、二階堂年恵、丹生英治「公民単元『国際連合について考える』-『国家・社会の形成者』を育成する中学校社会科授業の開発(2)-」『広島平和科学』、広島大学平和科学研究センター、第27巻、2005年、pp.137-154
(62) 田中伸「現代アメリカ社会科にみられる文化学習論の転換-教科書『比較文化(Comparing Cultures)』を事例として-」『広島大学大学院教育学研究科紀要第二部』広島大学大学院教育学研究科、第54号、2005年、pp.77-86
(63)池野範男、竹中伸夫、田中伸、二階堂年恵「小学校社会科における見方・考え方の育成方略-単元『地図とはどのようなものでしょうか?地図について考えてみよう!』を事例として-」『広島大学大学院教育学研究科紀要』第2部、広島大学大学院教育学研究科、第53号、2004年、pp.79-88
(64)田中伸「文化研究学習(Cultural Studies)としての社会学習原理」『教育学研究紀要』中国四国教育学会、第50巻、2004年、pp.392-397
(65)磯崎育男、田中伸、高内康司、上畑貴幸「『合理的』意思決定能力向上のために-試論として-」『千葉大学教育学部研究紀要』千葉大学教育学部、第52巻、2004年、pp.161-170
1. 全国社会科教育学会,学会奨励賞 2018年10月20日
(受賞論文:田中伸「コミュニケーション理論に基づく社会科教育論—『社会と折り合いをつける力』の育成を目指した授業デザイン—」『社会科研究』全国社会科教育学会,第83号,2015年11月,1-12ページ)
2. 公益財団法人消費者教育支援センター,優秀賞 2019年6月24日
(受賞教材:田中伸監修,公益社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会中部支部,前田佳洋,矢島徳宗,三浦寛之、大工泰裕,上野大介「自立する消費者のススメ」日本宝くじ協会,2019年2月
【科研費:代表者分】
(進行中の課題)
1)文部科学省科学研究費補助金(基盤研究B):研究代表者
研究課題名「不合意(dissensuss)と折り合いをつける過程を活用した授業開発研究方法論」
(課題番号20H01677)2020年度〜2024年度
2) 文部科学省科学研究費補助金
(ひらめき☆ときめきサイエンス~ようこそ大学の研究室へ~KAKENHI):研究代表者
研究課題名「社会を科学する!理想の社会を具体的にデザインし、政治家へ提案してみよう!」
(課題番号24HT0095)2024年度
(終了した課題)
3)文部科学省科学研究費補助金(萌芽的研究):研究代表者
研究課題名「文化学習改革論研究」
(課題番号18K18638)2018年度〜2022年度
4)文部科学省科学研究費補助金(国際共同研究加速基金):研究代表者
研究課題名「Dissensuss / consensus - handling of disagreement in dialogical learning」
(課題番号17KK0046)2017年度〜2020年度
5)文部科学省科学活動研究費補助金(若手研究(A)):研究代表者
研究課題名「コミュニケーション理論に基づく社会科教育論の構築」
(課題番号:15H05403)2015年〜2018年度
6)文部科学省科学研究費補助金(挑戦的萌芽研究):研究代表者
研究課題名「文化研究の論理に基づく社会科文化学習の改革研究」
(課題番号15K13224)2015年度〜2017年度
7)文部科学省科学研究費補助金
(ひらめき☆ときめきサイエンス~ようこそ大学の研究室へ~KAKENHI):研究代表者
研究課題名「社会を科学する!」(課題番号HT29171)2017年度
8)文部科学省科学研究費補助金
(ひらめき☆ときめきサイエンス~ようこそ大学の研究室へ~KAKENHI):研究代表者
研究課題名「社会を科学する!理想の社会をデザインし、政治家へ提案してみよう!」
(課題番号HT28166)2016年度
9)文部科学省科学活動研究費補助金(若手研究(B)):研究代表者
研究課題名「日本固有のシティズンシップに基づく社会科教育内容の開発・実践・検証・改善」
(課題番号:22730690)2010年〜2012年度
10)文部科学省科学活動研究費補助金(研究成果公開促進):研究代表者
研究課題名「現代アメリカ社会科の論理と展開-社会認識教育論から文化認識教育論へ」
(課題番号:225221)2010年度
11)文部科学省科学活動研究費補助金(若手研究スタートアップ):研究代表者
研究課題名「わが国の文化的文脈に則したシティズンシップ教育カリキュラム開発のための基礎的研究」
(課題番号:20830055)2008年〜2009年度
【科研費:分担者分】
(進行中の課題)
1)文部科学省科学研究費補助金(基盤研究(B))
「生徒と歴史教育との学習レリバンス構築に関する事例収集・分析とそのデータベース化」
(課題番号:19H01683)2019年度〜2024年度(代表者 二井正浩)
2)文部科学省科学研究費補助金(基盤研究(C))
「プロフェッション倫理と市民倫理の相克を活用した倫理教育のグローバル教材開発研究」
(課題番号:19K02752)2019年度〜2024年度(代表者 戸田善治)
(終了した課題)
1)文部科学省科学研究費補助金(基盤研究(C))
「教科指導における外国人児童生徒の教育支援に関する研究」
(課題番号:18K02818)2018年度〜2023年度(代表者 今井亜湖)
2)文部科学省科学研究費補助金(基盤研究(B))
「歴史的事象の特性を基盤とした社会科における必修単元『シティズンシップ』の開発研究」
(課題番号:15H03495)2015年度〜2019年度(代表者 戸田善治)
3)文部科学省科学研究費補助金(基盤研究(B))
「資質・能力の多様性と学際性を視点にした地理歴史授業の国際協働開発と教師への普及」
(課題番号:17H02704)2017年度〜2020年度(代表者 伊藤直之)
4)文部科学省科学研究費補助金(基盤研究(B))
「社会系教科目における価値学習の開発研究」
(課題番号:15H03507)2015年度〜2017年度(代表者 大杉昭英)
5)文部科学省科学研究費補助金(基盤研究(B))
「教科教育学のパラダイムと社会的責任の国際比較-社会科教育研究者が果たす役割とは-」
(課題番号:15H03504)2015年度〜2017年度(代表者 草原和博)
6)文部科学省科学研究費補助金(基盤研究(C))
「歴史的思考と理解の一体的形成を促すエンパシー(共感)の指導と評価に関する研究」
(課題番号:15H04431)2015年度〜2017年度(代表者 原田智仁)
7)文部科学省科学研究費補助金(基盤研究(C))
「市民性を基盤とした「調停する力」の育成を目指す道徳の授業開発」
(課題番号:15H04491)2015年度〜2017年度(代表者 須本良夫)
8)文部科学省科学研究費補助金(基盤研究(C))
研究課題名「社会認識に基盤を置いたシティズンシップの実体化およびその再構築モデルの開発研究」
(課題番号:24531102)2012年度〜2014年度(代表者 戸田善治)
9)文部科学省科学研究費補助金(基盤研究(B))
研究課題名「米英独における評価の高い歴史授業の収集・分析とそのデータベース化」
(課題番号:24402049)2012年度〜2014年度(代表者 二井正浩)
10)文部科学省科学研究費補助金(基盤研究(C))
研究課題名「観察・コミュニケーション能力指標の構造化による幼小縦断科学教育カリキュラムの開発」
(課題番号:24531037)2012年度〜2014年度(代表者 小谷卓也)
11)文部科学省科学研究費補助金(基盤研究(B))
研究課題名 「「活用」力の段階的・系統的育成を目指した社会系教科目の授業開発発」
(課題番号:23330257)2011年度~2014年度)(代表者 大杉昭英)
12)文部科学省科学研究費補助金(基盤研究(C))
研究課題名「観察・コミュニケーション能力の育成を目指した保幼小連携科学カリキュラム の開発」
(課題番号:23531092)2011年度~2013年度(代表者 長瀬美子)
13)文部科学省科学研究費補助金(基盤研究(C))
研究課題名「市民性概念の歴史的比較教育的検討に基づく市民性教育内容開発」
(課題番号:22330249)2011年~2013年度(代表者 釜本健司)
14)文部科学省科学研究費補助金(基盤研究(B))
研究課題名「中等社会系教科における歴史総合・地歴相関カリキュラムに関する国際調査・開発 研究」
(課題番号:23330258)2011年度~2013年度(代表者 原田智仁)
15)文部科学省科学研究費補助金(基盤研究(B))
研究課題名「社会科教育研究・実践の改善に資する『研究法ハンドブック』の日米共同開発
(課題番号:22330249)2010年~2012年度(代表者 草原和博)
【その他助成金等】
(進行中の課題)
1)上廣倫理財団教育研究活動助成
研究科題名「 子どものための哲学教育カリキュラム研究プロジェクト」
2021年度~(代表者 田中伸)
2)兵庫教育大学大学院学校教育学研究科共同研究プロジェクト
研究課題名「教科指導におけるSTEAM教育の多様性と汎用性に関する国際調査研究」
2022年度~2025年度(代表者 菅井三実)
(終了した課題)
1)日本私立学校振興・共済事業団助成 学術研究振興資金
研究課題名「幼児期における科学教育カリキュラムの開発—実践モデルならびに評価方略の開発・実践・検証を通して−」2012年度〜2014年年度(代表者 長瀬美子)
2)兵庫教育大学大学院学校教育学研究科共同研究プロジェクト
研究課題名「社会系教科目の授業実践を支援する学習材の開発 −教師・学習材・子どもの相互関係の解明をめざして−」 2009年度~2011年度(代表者 西村公孝、草原和博)
3)サントリー文化財団研究助成
研究課題名「シティズンシップ教育の役割と方法に関する日米英国際比較調査」
2009年度~2010年度(代表者 桑原敏典)
Copyright © 2023 Nobolabo. All rights reserved
